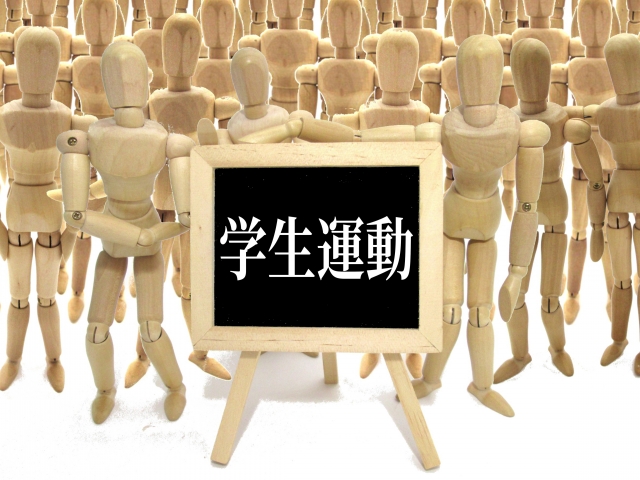日本では、条文には載っていない権利が保障されることがあります。
そんな人権のなかに「知る権利」という人権があります。聞いたことありませんか?知る権利。
このページではその「知る権利」について解説したいと思います。知る権利とはどんな権利か、根拠の人権は何条かなどを解説したいと思いますので、興味がある方はどうぞお付き合いください。
知る権利とは
知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、または、国家に対し情報の公開を請求する権利をいいます。ちょっと抽象的な言い回しですが、とりあえず大筋ではこんな感じです。
知る権利とは何条が根拠となるの?
日本国憲法の条文をなめまわしても、「知る権利」なる文言は出てきません。でも知る権利は保障されているのですが、どういうことなのでしょうか。
実は知る権利とは21条の表現の自由により保障されているとされます。
「知る」ということは、決して「表現活動」とはいえないと思うのですが、なぜ知る権利が21条の表現の自由として保障されるのでしょうか。
表現の自由と知る権利の関係性について
一般論として、表現活動とは、「受け手」の存在が前提になっています。歌手でいえば、オーディエンスやリスナーの存在あってこその表現活動。ただの1人も聴いてくれる人がいないのは、歌えればいいという歌手もいるかもしれませんが、表現活動としてはあるべき姿ではないと思います。小説家等の物書きだって、読んでくれる人がいて初めて表現活動といえるのではないでしょうか。
視点変えて、あなた個人目線で考えてみてください。
あなたが表現活動をするには、何らかの情報の入手が不可欠です。全く何もないところから表現活動は難しい。
例えば、あなたが何らかの政治的意思(政府批判ということにしておきます)をブログなり街頭なりで表明するとします。その意思表明ができるのは、何らかの形で政府の行為・発表等を知ったからではないでしょうか。某国と友好関係の条約を締結するとかなんとか。
このように、表現活動には情報の受け取りが前提であり密接不可分の関係性なのです。
情報の受領=知る権利も保障すべき
以上のように、表現活動とはすなわち情報の連鎖。「情報コミュニケーション」ともいえます。コミュニケーションですから、「表現者」と「受け手」という表裏一体の存在が必要なわけです。
21条で保障されている表現活動を保障するには、情報の受領すなわち知る権利も一体として保障すべき、でなければ瑕疵ある表現活動になってしまうという図式です。
間違った情報の受領では間違った表現活動になってしまうし、そもそも。情報が入ってこないのでは表現活動すらままならない。国外の昨今のニュースを観れば、火を見るより明らかです。だから、情報の受領は、表現活動自体の少なくとも同等の重大要素なのです。
知る権利3つ顔とは
知る権利には、3つの顔があります。同じ権利でもちょっと性格が異なる権利を併せ持っています。
- 自由権的側面
- 請求的側面
- 参政権的側面
知る権利の自由権的側面とは
知る権利の自由権的側面というのは、国民が国家の妨げなく自由に情報を受け取る権利のことです。
例えば、インターネットの情報に対して公権力が何らかの規制を掛けるというものがあります。国家権力にとって何か都合の悪い情報を何らかの形で閲覧できなくするとか、そういうことですね。国家に対して「余計なことに介入しないでくれ。規制されると知りたいことも知れなくなる」という自由、権利です。
知る権利の請求権的側面とは
知る権利の請求権的側面とは、公権力が保有する情報の開示を請求する権利です。国家にとって国民に知れると都合が悪い情報があったとします。そういった情報を「知りたい!開示請求するからな?」という自由、権利です。
情報公開法は請求権的側面の表れ
現在、情報公開法という法律があります。この法律には、「知る権利」という言葉は用いられていませんが、この知る権利の請求権的側面の趣旨が妥当するものと言っても差し支えないでしょう。
知る権利の参政権的側面とは
知る権利の本来の趣旨を達成し表現活動とその先は自身が政治に参加するという参政権的側面も併せ持っています。選挙での投票行動は立派な参政権行使です。自分が得た情報を精査し政治に反映させる、これは知る権利の本来の趣旨と言えるでしょう。
知る権利の重要判例
以上の知る権利についての言説は基本的に学説をまとめたものですが、裁判ではどうなっているのでしょうか。知る権利についての最高裁判例で重要なものは「博多駅テレビフィルム提出命令事件(昭和44年11月26日最高裁判決)」でしょうか。
これは裁判所が報道機関に法律(刑事訴訟法)に基づいて撮影されたフィルムの提出を命じた事件です。この命令が21条に抵触するということですが、知る権利が正面切って争点になったというわけではなく、表現の自由・取材の自由が問題になった事件で、その過程で知る権利にも触れているというものです。
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、需要な判断の資料を提供し、国民の知る権利奉仕するもの~事実の報道の自由は憲法21条のもとにある
このように、知る権利は21条で保障されているとしています。
知る権利の公共の福祉による制約
知る権利は21条で保障されていると言っても例によって100%保障されているわけではなく、制約があります。これも公共の福祉の一環になりますね。
表現の自由は、場合によって対象が他人に関わることに事も多いため、13条のプライバシー権と衝突する場面が多くなります。知る権利もその例に漏れません。他人のプライバシーにかかわることを知りたいというのは人情であるとは理解できますが、だからと言って、知られる方はたまりません。そんなの勘弁してよ?という話です。
いくら知る権利があるといっても、むやみやたらに他人のプライバシーを暴いても良いということはないですし、情報開示請求でも、個人的プライバシーに係る情報には情報公開法で規制されています。
問題意識として
この13条と21条の衝突はバランス感覚が大事だと思います。つまり、個別具体的に検討していくということです。
典型例なのは一般人・公人の個人情報の取り扱いの差です。
ある特定の芸能人がどんな人と付き合っているかという下世話なものから、宗教団体に属しているか、日本人のように振る舞っているけど日本人ではないのか、こういうことは私も興味がないというとウソになりますが、単なる個人的好奇心を満たすものとして、プライバシーの保護に偏っても良いのではないかと思います。
芸能人は有名人ではあるが一般人ですからね、法に触れるようなことでなければ、好きにしてもらったらいいと思います。
しかし、これは公人となると話は変わります。特定の政治家の出自は知りたい情報だと思いますし、国民主権原理から考えても明らかになるべき事項でしょう。具体的には外国人参政権や公務就任権の話と関係してきますが、日本国民ないし有権者にとって、大きな判断材料となり得るものです。
知る権利とは、国民の表現の自由の保障の前提としてきわめて重要な権利です。しかし、13条との対立を意識しつつ、バランスを保つという問題意識が必要なのではないでしょうか。
まとめ
以上、知る権利についてお話させていただきました。
まずは知る権利が何で必要なのかを表現の自由と絡めて理解しておくと良いと思います。
また、知る権利と他人権との考え方についての問題意識はテレビやSNS等で情報を得ている方々にとって、ヘンな「流れ」に自分が持っていかれがちの方は頭の片隅にでも保存しておいてください。