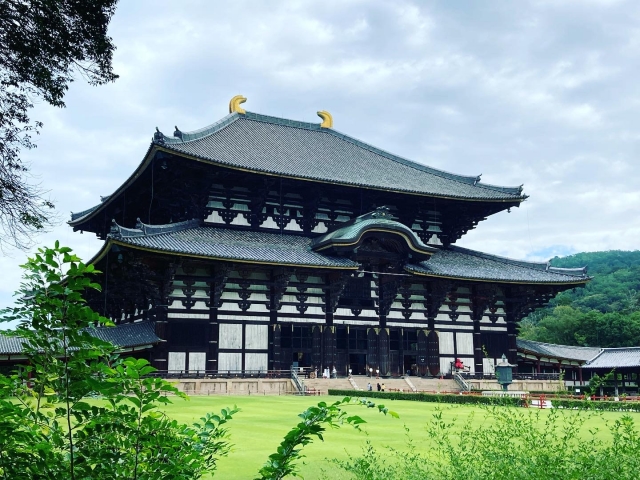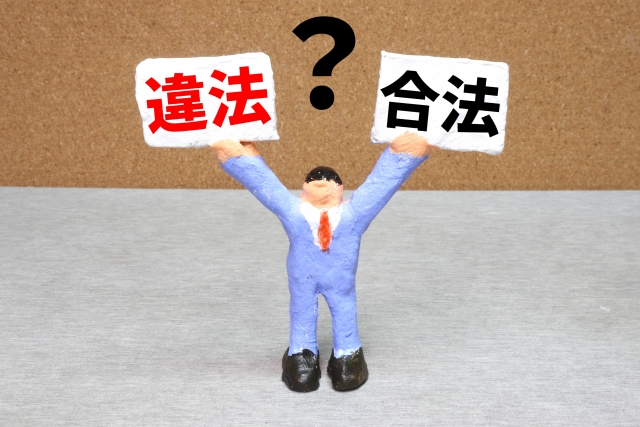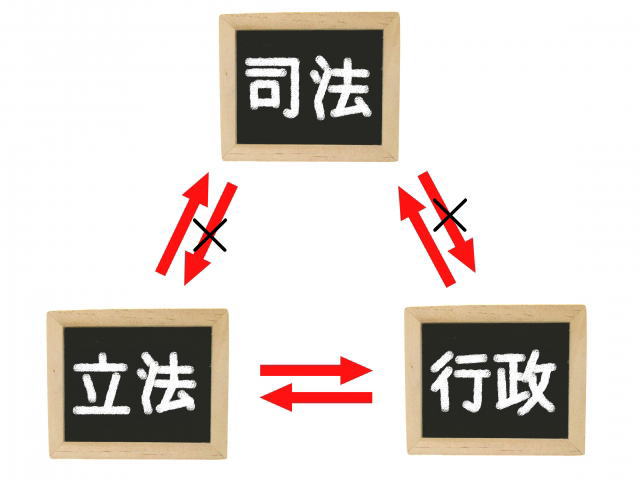ご存知のように、現在、日本と米国は日米安全保障条約を締結していますが、まあ賛否両論です未だに。
その是非については置いておいて、我が国において日米安全保障条約について司法審査が初めて行われた「砂川事件」と言う裁判を解説したいと思います。ちょっと古い事件なのですが、令和の今でも踏襲されている、憲法学上重要な判例です。
わかりやすく解説しますので、興味があればお付き合いください。
砂川事件の論点とは
事件解説に行く前に、当該判例の論点について確認しておきましょう。砂川事件を学ぶにおいて確認しておきたいことは、安全保障条約に司法審査は及ぶのか?ということ。これが砂川事件の論点です。
この事件の舞台は駐留米軍施設内であり、それが日米安全保障条約の合憲性に発展してしまいます。そこに司法のメスは入るのか否か、つまり、司法権の限界案件であるということ。
- 安全保障条約に司法審査は及ぶのか
- 及ばないとしたらどういう規範によるものなのか
この2点意識して先にお進みいただければと思います。
事案
昭和32年7月、東京都砂川町(現立川市)の駐留米軍使用の立川飛行場の拡張の測量に反対するデモ隊が基地内に侵入。これが刑事特別法2条(米軍が使用する施設または区域を侵す罪)に問われ起訴されました。
砂川事件第一審
第1審の東京地裁(昭和34年3月30日)は、駐留米軍は9条2項違反であり違憲であるとし、違憲である駐留米軍の法益保護を担う刑事特別法が、軽犯罪法より重いのは憲法31条に違反しているから被告人は無罪という判決を出しました。
この図式お分かりでしょうか。その駐留米軍の利益を守る刑事特別法2条違反が、軽犯罪法違反より罪が重いのはバランスが悪い、刑事罰の適正化を定めた憲法31条違反だ!という理屈です。
これに対し、検察官は最高裁へ跳躍上告。
跳躍上告とは
検察は訴訟テクニックを行使することにしました。跳躍上告です。跳躍上告とは、第一審から控訴という通常の流れをすっ飛ばして、最高裁判所へ戦いの場を求めること。
第一審判決が国の憲法解釈と相いれない見解を示したので、最高裁に違憲立法審査権の行使を委ねるということです。根拠は刑訴法406条、刑訴規則254条。
検察は跳躍上告審で、
- 81条には「条約」に触れられていない(条約が違憲審査の対象か不明)
- 条約が81条の対象如何に関わらず日米安保の特殊性を鑑み違憲審査の対象を考えるべきでない
と主張。
砂川事件最高裁判決
原判決破棄、審理やり直しということで地裁に戻される判決です。以下重要部分の判旨要約。
本件安全保障条約は~主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
右駐留軍隊は外国軍隊であつて、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となつてあだかも自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らか~
この軍隊は~同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり~極東における国際の平和と安全の維持に寄与し~その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならない~
かようなアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効があることが一見極めて明白であるとは、到底認められない
砂川事件判決解説
当該事件は、日米安全保障条約の憲法適合性についての司法判断および統治行為論を適用した最初の裁判です。
その意味では、当該裁判における憲法学的役割は、1段落目、2段落目でほぼ終了しているのかな、と。
判旨①:日米安保条約の司法判断について
1段目、日米安全保障条約に関する国家行為は「高度の政治性を有するもの」と認定し、その法的判断については政府や国会が責任を持つべきではないか?(裁判所が判断すべきじゃないんじゃないかな?)と、後の言説の伏線を張っています。統治行為論や自由裁量行為という、司法権の限界案件を示唆していますね。
司法権の限界とは、事情により司法審査できない(しない?)領域の問題ですが統治行為論も自由裁量行為も司法権の限界の類型です。→ 司法権と法律上の争訟を判例で解説 !司法権の限界類型も
判旨②:統治行為論?自由裁量行為?
2段落目。日米安保は高度な政治行為であるから(1段落目)、司法審査はなじまないとしました。示唆した通りですね。
この部分は統治行為論による司法審査回避と取れますが「なじまない」と消極的な表現に留めているのがポイント。以下で曖昧表現にした理由が見て取れます。すなわち、
「一見極めて明白な違憲無効と認められる場合は司法審査はあり得るがでなければ司法審の範囲外」という規範です。自由裁量行為のように政府の行為を一定の範囲内での介入を避けつつ。
以下、民主主義にて解決すべき問題であるとしていることから、ベースは統治行為論を根拠にして自由裁量行為を弾力性を持たすというイメージでしょうか。
判旨③:あてはめ
この先は当てはめです。当然米軍の指揮権は日本側にあるわけでなく、米側にあるもの。日本政府が好きに動かすことはできません。米軍が駐留しているのはわが国の防衛力を補うものであって、それは前文、9条の趣旨に適合するものとしています。
そして、それは、「一見極めて(違憲無効であることが)明白であるとは、到底認められない」としています。自由裁量行為の見地からすれば、裁量範囲内、よって、司法審査はしないということですね。
余談-集団的自衛権の見解
せっかくなんで、3段落目以降もコメントしておきましょう。これは私的な解説です。
3段落目以降、読んで頂ければお分かりになると思いますが、軍事同盟国であるアメリカとの集団的自衛権についての最高裁の見解になります。
当事件で統治行為論を持ち出したのも、安全保障の問題は、「違憲無効があることが一見極めて明白」でなければ、憲法の問題として語るべきではないという価値判断からだと考えます。
裁判所は、集団的自衛権について、合憲違憲の判断はすべきではない、と。
判旨では、明らかに集団的自衛権を肯定的に捉えています。だから、政府の裁量権の範囲内だとしているのですね。
だから、合憲違憲の判断は避けた。理由は前述のとおりです。安全保障の問題は、よほどのことがない限りは、憲法判断に巻き込むべきではないということなのでしょう。
砂川事件結果
最高裁は上告破棄し地裁に審理差し戻しされる判決が出ました。その差戻審ではデモ隊の行為は逆転有罪になり後に罰金刑が確定しました。
こうなると、最初の地裁の判決は何だったんだ、という感じですね。
まとめ
以上が砂川事件の解説です。
この事件は日米安保の合憲性について触れた最初の裁判ですが、統治行為論を持ち出した最初の裁判です。まあ、結果的に司法判断していないので触れたにとどめる以外言いようがないと思うのですが、それも一つの結論なのかなと思います。
いずれにしても、難しいというかわかりづらいというかしっくりこないと思う方も少なくないと思います。もう60年以上前の判決ですから、新しい機軸が出ても良い時期かなという独り言。